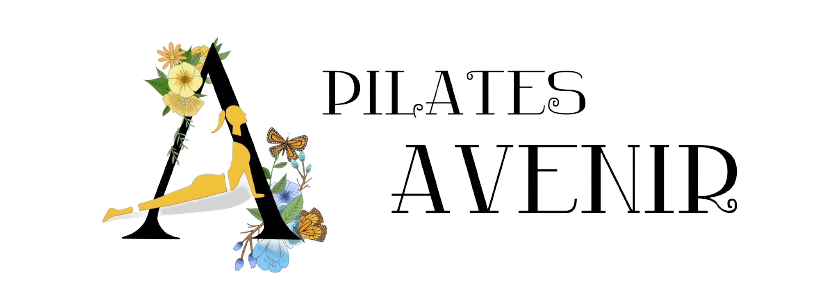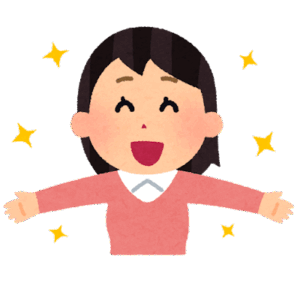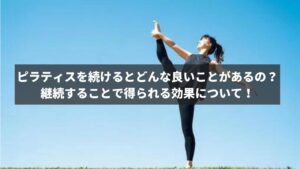一年の中でも気温や湿度がピークを迎える8月。暑さや生活リズムの乱れによって、体にさまざまな不調が現れやすい時期です。夏バテという言葉があるように、気温や環境の影響は心身にダイレクトに響いてきます。ここでは、8月に起こりやすい体の不調と、その対策についてご紹介します。
1. 夏バテ・食欲不振
真夏の強い日差しと高温多湿の中で過ごすと、自律神経が乱れやすくなり、体がだるい、やる気が出ないといった「夏バテ」の症状が出てきます。特に冷たい飲み物やアイスを摂りすぎると胃腸が冷えて働きが弱まり、食欲不振につながります。対策としては、冷たいものばかりに偏らず、温かいスープや消化に良い食材(おかゆ、うどん、豆腐など)を意識して取り入れることがおすすめです。
2. 冷房による冷え・頭痛
外は猛暑なのに、室内はクーラーで冷えすぎている。この温度差も大きな負担になります。長時間冷房の効いた場所にいると、手足が冷える、頭痛や肩こりが出ることも。特に女性は冷えによってむくみや生理不順につながることもあるので要注意です。羽織りものを持ち歩く、就寝時はお腹や腰を冷やさないようタオルケットを使うなど、冷え対策をしましょう。
3. 脱水症状・熱中症
8月は気温も湿度も高く、汗を大量にかくことで体内の水分とミネラルが失われやすくなります。のどが渇いていなくても、こまめに水分を摂ることが重要です。水だけでなく、塩分やミネラルを含む経口補水液や麦茶などを取り入れるとバランスが保ちやすくなります。めまいや立ちくらみ、頭痛が出たときは熱中症のサインかもしれないので早めに休みましょう。
4. 睡眠の質の低下
夜になっても気温が下がらず、寝苦しさから睡眠不足になりがちです。冷房を適切に使うことはもちろん、寝る前のスマホを控えてリラックスする時間を作ることも大切です。眠りが浅いと体の回復が追いつかず、日中のだるさや集中力低下につながります。
5. 胃腸トラブル
夏祭りやバーベキューなどで食事の機会が増える8月は、つい食べすぎ・飲みすぎになりやすい時期です。冷たいビールや揚げ物などの刺激物は胃腸に負担をかけます。翌日に胃もたれを感じるときは無理に食べず、白湯やお粥などで胃腸を休ませましょう。
まとめ
8月は「暑さ」と「冷え」、そして「生活リズムの乱れ」が体の不調を引き起こす大きな要因です。夏を元気に乗り切るためには、冷たいものと温かいもののバランスをとること、室内外の温度差に気を配ること、そしてしっかりと休養を取ることが欠かせません。小さなセルフケアを積み重ねて、残暑も健やかに過ごしましょう。
次回、ピラティスのセルフケア方法☝🏻✨